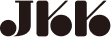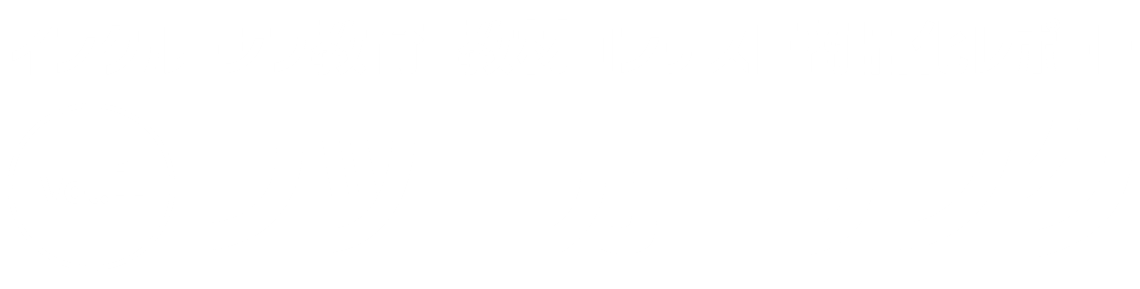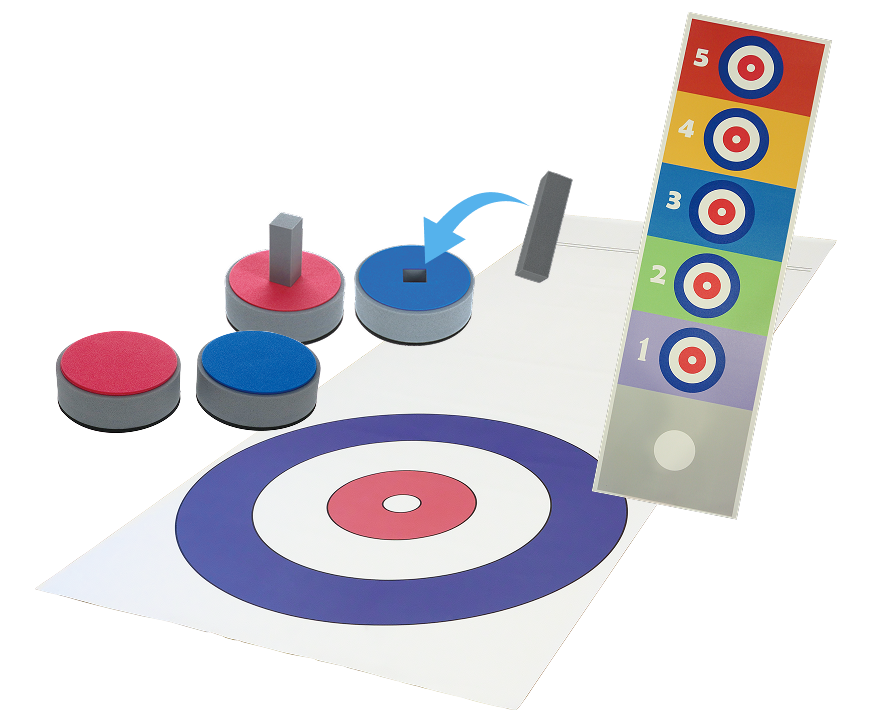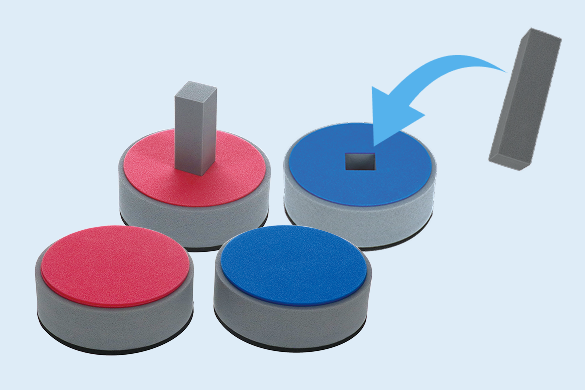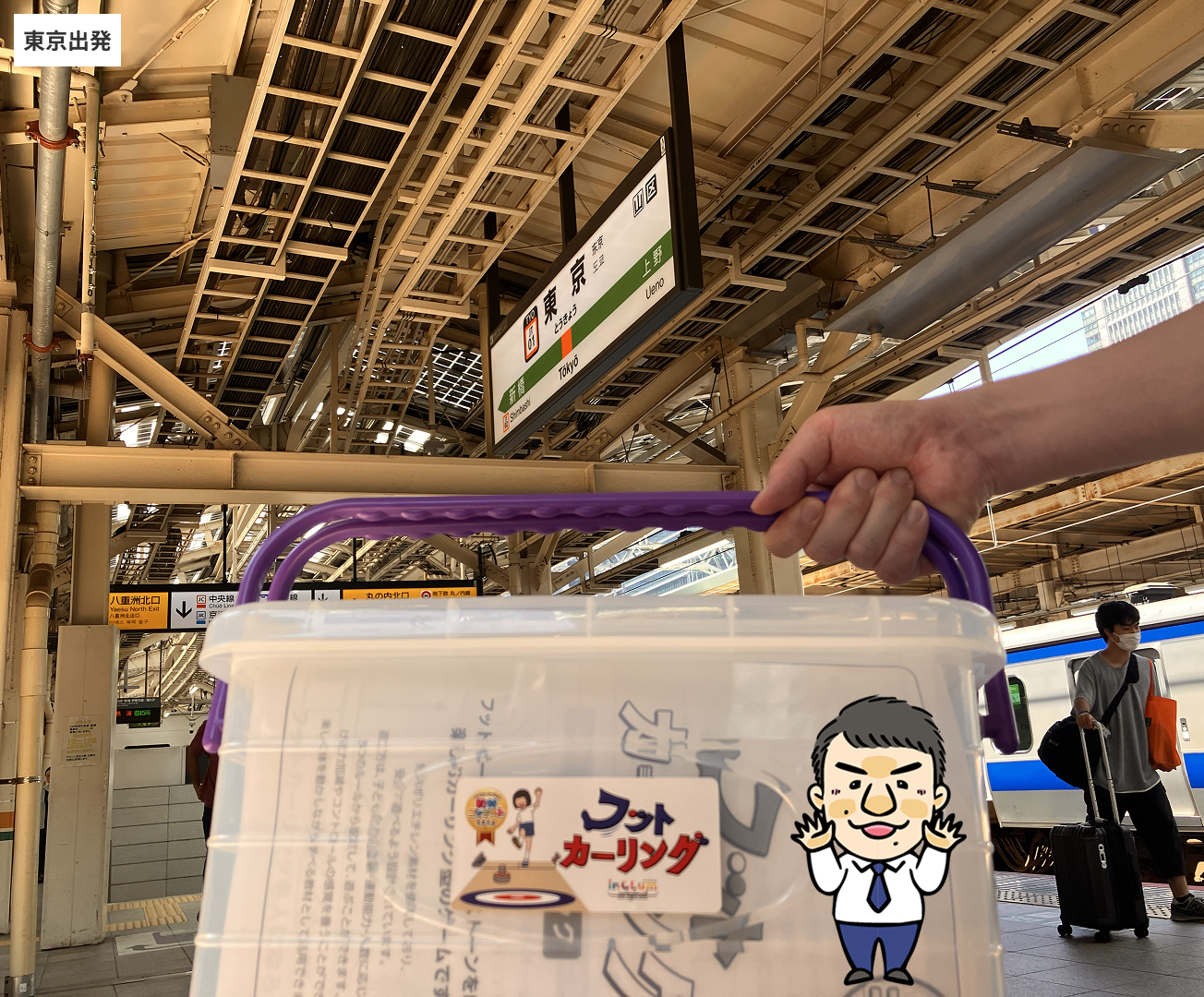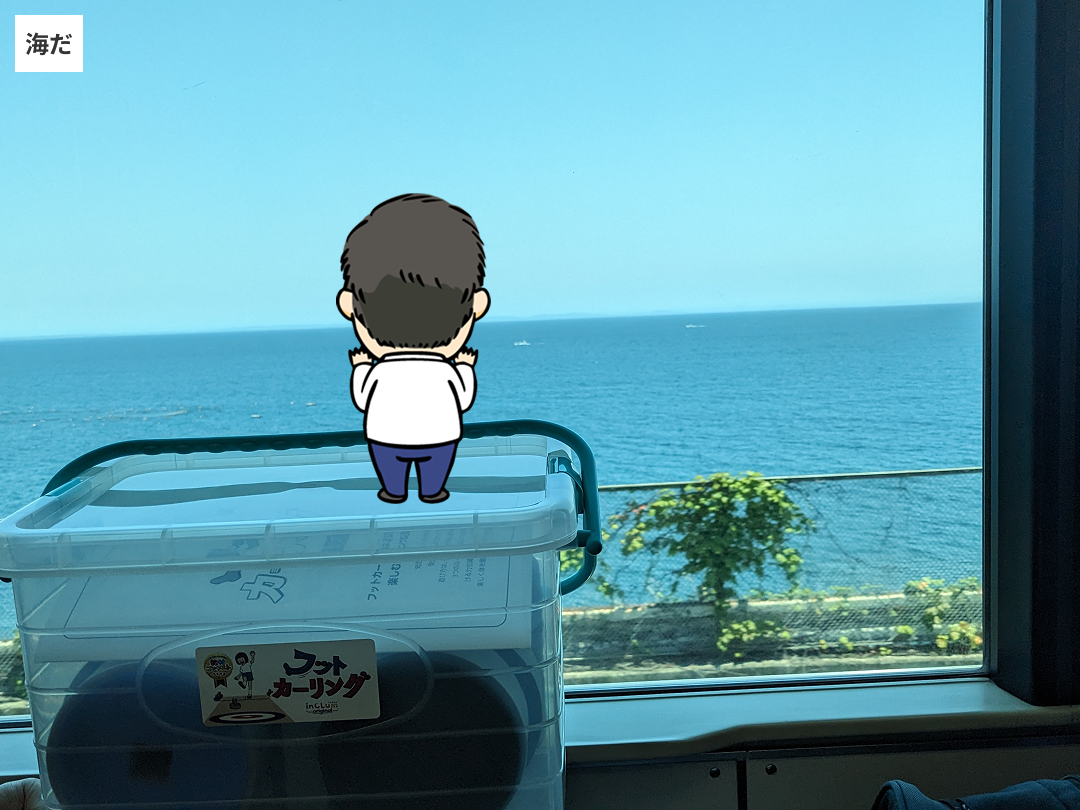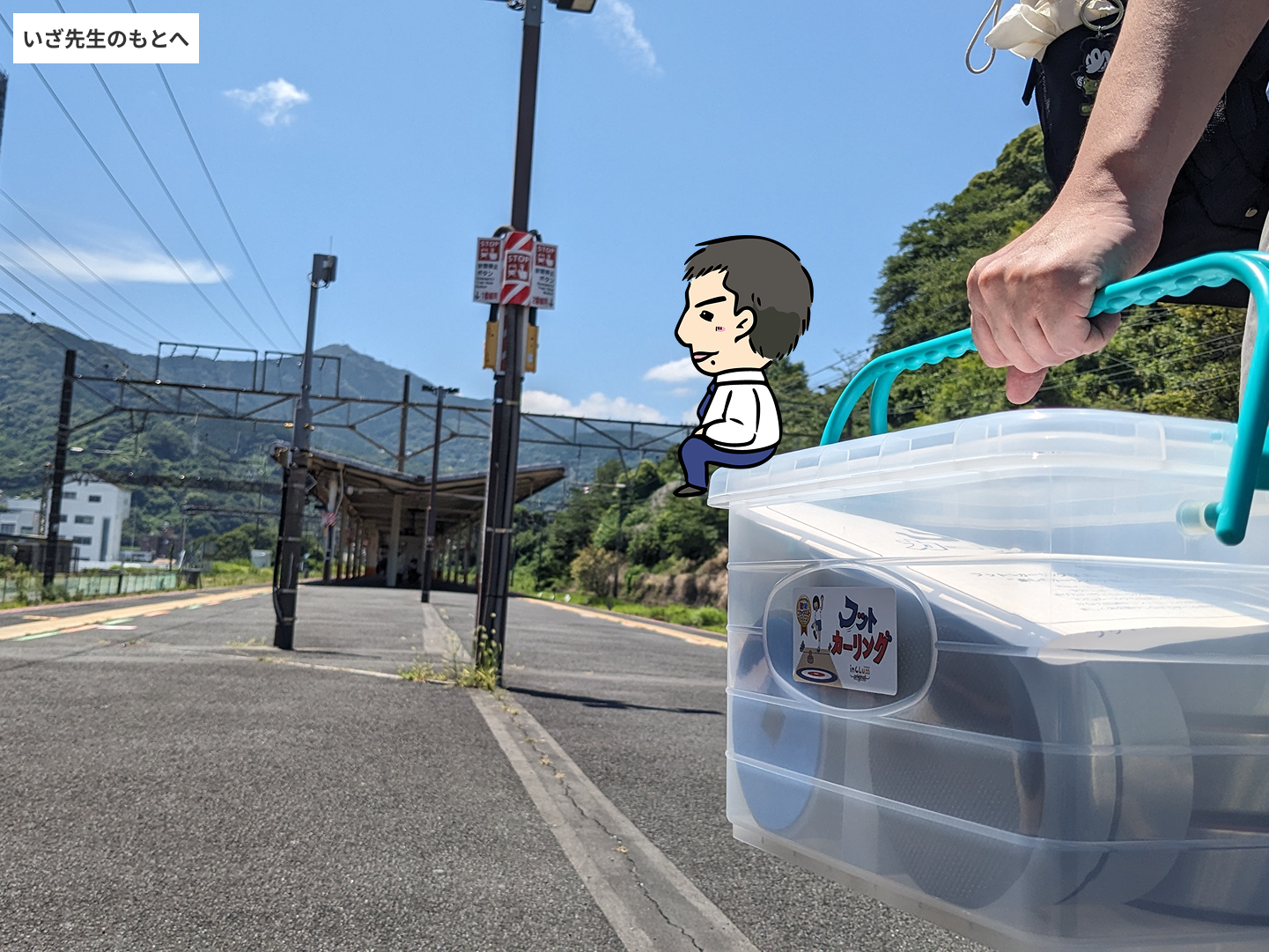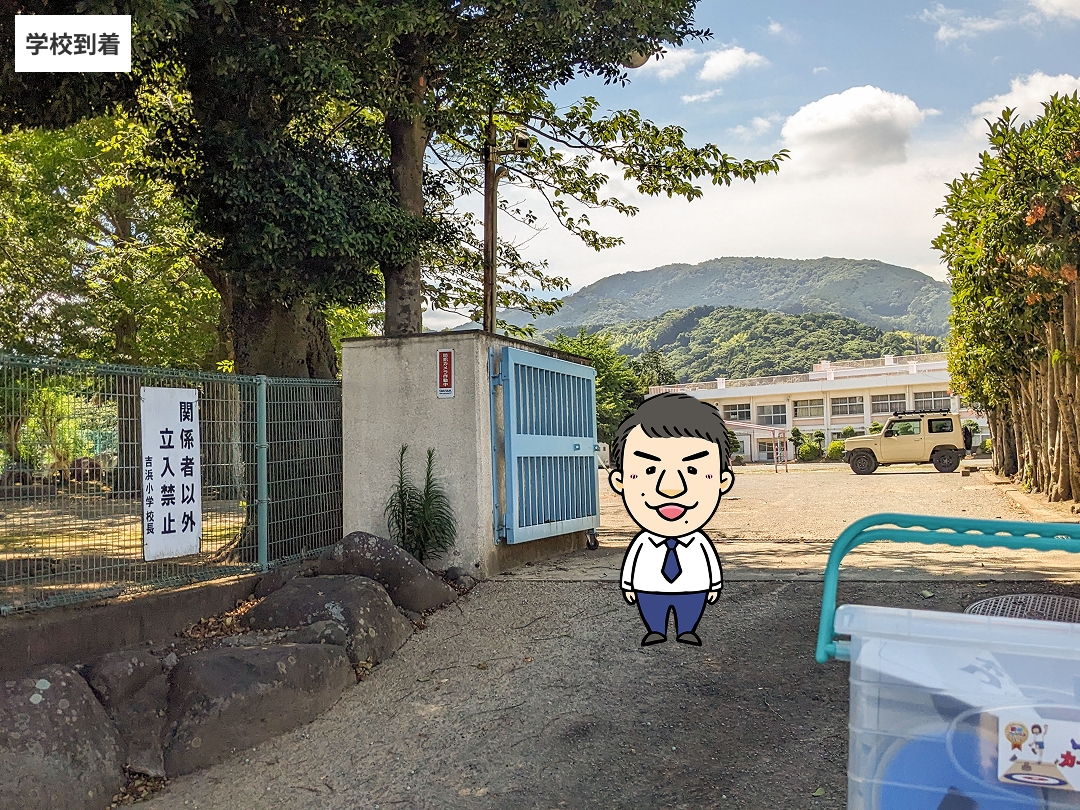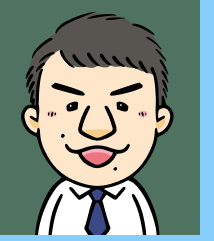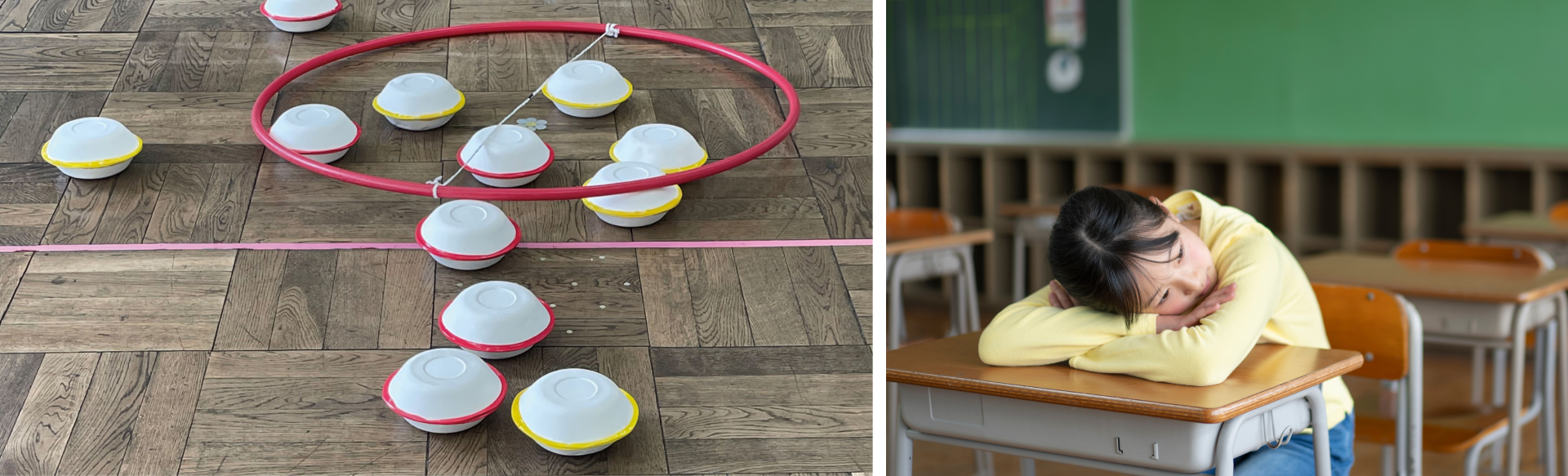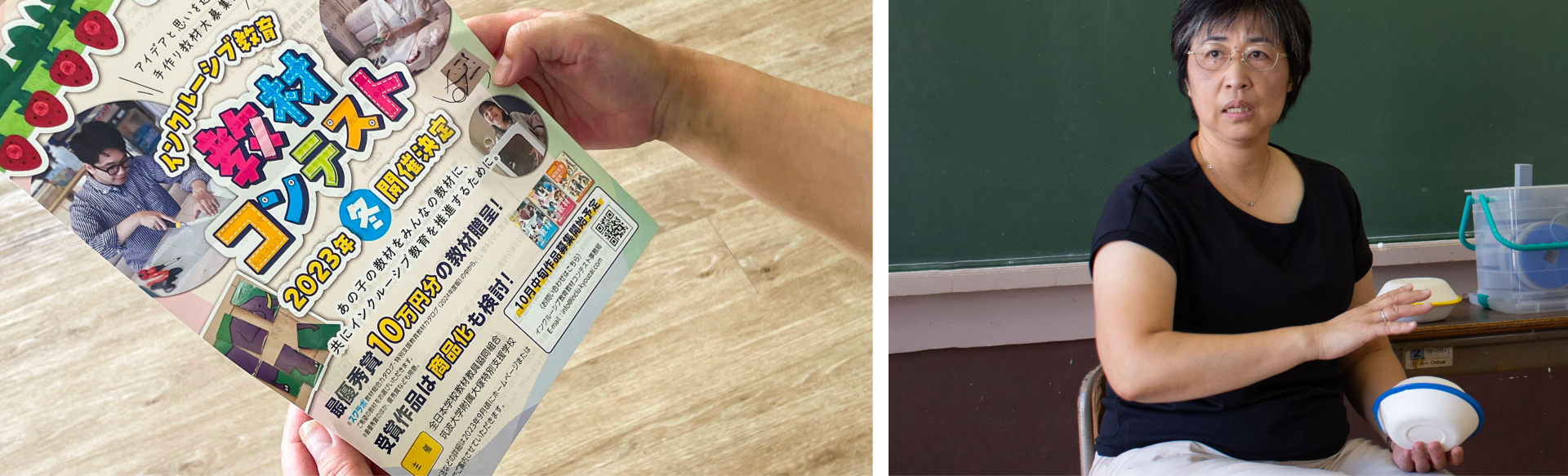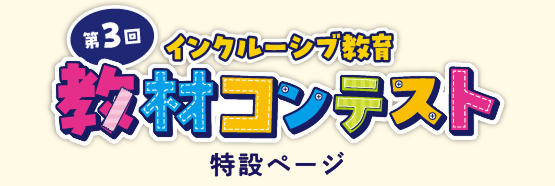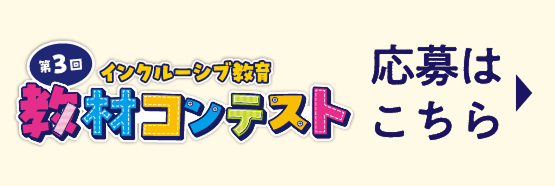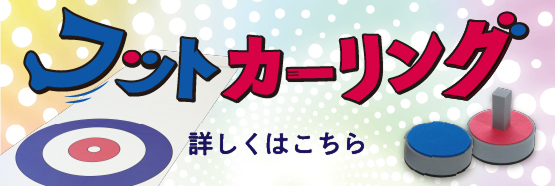01
教材づくり
-

さとう君 先生は普段から教材をお作りになっているそうですが。
-

早川先生 はい、教材は自作することが多いです。
-

清水先生 頼んで作ってもらうと、ニュアンスというか細かな点が変わってしまうので…。
-

さとう君 「教材は作る」がベースなんですね。
-

清水先生 カタログを見て、これ作れそうかなと思ったら、子どもたちに合わせて調整します。
-

さとう君 カスタマイズですか。
-

早川先生 高いからなかなか買えないし(笑)。買ったものだと、教材に子どもたちが合わせてしまうということもあるので、なるべく作りたいんです。それに教材づくりは楽しいですよ!